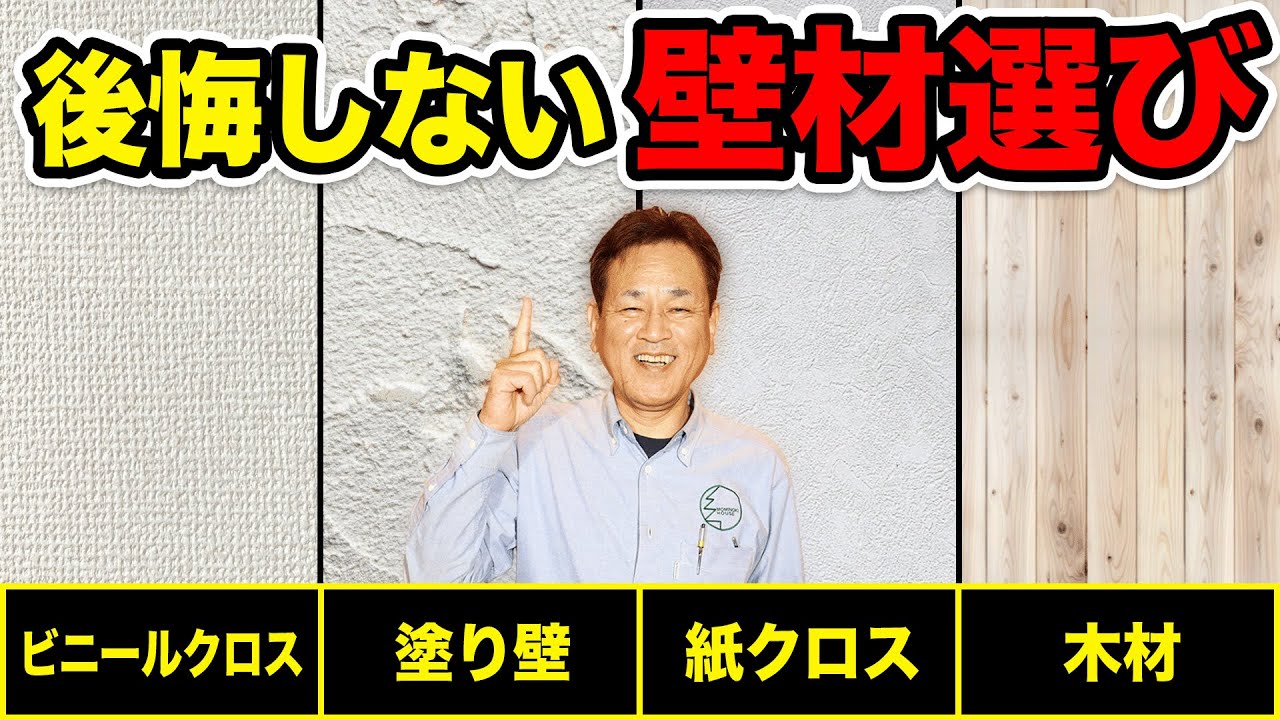壁材には様々な種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。特に内装用の壁材は、室内の雰囲気や空気環境に大きな影響を与えるため、適切な選択をしないと、快適性や健康面に影響を及ぼす可能性があります。
本記事では、「もみの木ハウス・かごしま」さんの解説動画を参考に、主要な壁材の種類と選び方のポイントについて解説します。
壁材選びに悩んでいる方や、家の空気環境への壁材の影響について知りたいという方は、ぜひ最後までご覧ください。
壁材その1:ビニールクロス
壁材の1つ目は、ビニールクロスです。
ビニールクロスは最も定番の内装用壁材で、日本の住宅の約90%がビニールクロスを使っているとも言われています。
ビニールクロスのメリット、人気の理由は、値段がお手頃なことと、見た目の種類が豊富に選べておしゃれな室内にしやすいということがあります。掃除がしやすいのもビニールクロスのメリットです。
さらに建築会社目線で見た場合、ビニールクロスは施行がしやすく、お客様からのクレームにもなりづらいため、採用しやすいという事情もあるようです。
ただし、ビニールクロスにもデメリットはあります。
最も大きなデメリットは、化学物質が揮発することです。
ビニールクロスには可塑剤(材料を加工しやすくするために添加される物質)として、重金属のヒ素・水銀・鉛・セレン・カドミウム・水銀などが含まれています。
これらが室内の空気に揮発し、その空気を住んでいる人は吸い込むことになります。
また、これらの重金属類は約10年で揮発し終わってしまうため、その後は壁材の表面がボロボロと剥がれてくるということもあります。そのため、一般的なビニールクロスの耐用年数はだいたい10年と言われています。
日本では90%の住宅で使われているこのビニールクロスですが、海外での使用率は10%に満たないとも言われています。
これは文化的な違いや美意識の違いによる理由もありますが、室内環境への意識が高いということも理由にあるようです。
壁材その2:塗り壁
壁材の2つ目は、塗り壁です。
塗り壁にも種類があり、珪藻土や漆喰などが主な塗り壁です。
塗り壁のメリットの一つは、補修や張り替えがいらないということです。
また、湿気を通す素材のため室内の調湿を行ってくれるのも塗り壁のメリットです。
さらに、塗り壁の見た目そのものが豪華に見えて人気があるということもメリットの一つです。
一方、塗り壁のデメリットとしては、「バインダー」というつなぎ剤が入っているということです。
つなぎ剤が入っていないと塗り壁はボロボロと剥がれてきてしまうため、基本的にはつなぎ剤が含まれています。
つなぎ剤は主にアクリル樹脂が使われることが多いため、塗り壁とは言え自然素材100%ではありません。そして、このアクリル樹脂から化学物質が揮発する場合があります。
またアクリル樹脂は静電気を帯びやすいというデメリットもあります。
塗り壁の見た目が好みの方にとっては、壁材の選択肢となります。
ただし塗り壁はビニールクロスの約2〜3倍の価格となるため、コスパ重視であれば塗り壁調のビニールクロスを使うという選択肢もあります。
住む人の健康や室内の空気環境を考えた場合は、必ずしも塗り壁が選択肢になるわけでは無いということのようです。
壁材その3:紙クロス
壁材の3つ目は、紙クロスです。紙クロスとは、いわゆる「壁紙」のことです。
紙クロスには「オガファーザー」や「土佐和紙」などの種類があります。
紙クロスのメリットとしては、化学物質が出にくいということと、呼吸するため湿気を通しやすいということです。
また価格的にも、ビニールクロスよりは少し高いものの、塗り壁などと比べると安い部類に入ります。
紙クロスのデメリットとしては、汚れに弱いということです。
汚れ防止や防カビ剤などが入っていないため、他の壁材よりも汚れに弱く、放置するとシミになる場合もあります。
特にスイッチ周りなどの手が触れる機会が多い場所は、黒く汚れやすいです。
汚れを補修する場合は、その壁紙の上に新しい壁紙を貼り直すしかありません。
ただし紙クロスの「オガファーザー」は新聞紙とおがくずでできた塗装下地材のため、汚れてきたら塗装をかけることできれいな状態に戻せるため、通常の紙クロスより楽に補修できます。
化学物質がほとんど揮発しないため、住む人の健康面を考えた場合は紙クロスが選択肢に入ってきます。
ただし、汚れ防止や防カビなどの機能はないため、機能性を重視する場合は他の壁材を選ぶことになります。
壁材その4:木材
壁材の4つ目は、木材です。
木材にはスギ・ヒノキ・マツなど多くの種類があります。
木材の壁材・内装材のメリットは、木の種類によって様々な効能があり、適切に使えば健康に良い効果がある場合があるということです。
また、木目調のデザインの人気も木材を使うメリットになります。
木材の効能としては、例えば杉は破傷風菌を殺す、ヒノキは殺菌作用があるなど、木の種類によって様々です。
ただし木の効能を活かした家づくりをする場合は、木材の乾燥方法が自然乾燥であることが重要です。人工乾燥の木材は、その木の効能が抜けてしまっていると考えて良いとのことです。
自然乾燥の木材でなければ木の効能を活かせない反面、木目調のデザインのみが目的であれば人工乾燥でも良いということにもなります。
また自然乾燥の柾目の木材であれば、調湿効果も望めます。
木材の壁材のデメリットは、使い方を間違えると人体に悪影響がある場合もあるということです。
先ほどメリットとして挙げた殺菌作用なども、室内に自然乾燥の木材を大量に使いすぎると、人体に対して悪影響を及ぼす場合があります。
また、無垢の木材からも化学物質が揮発していて、これが適切な量であればリラックス効果などがありますが、濃度が高すぎると人体に影響を及ぼす可能性があります。
ホルムアルデヒドなどの濃度が高いとシックハウス症候群の原因となる可能性があるため、TVOC(総揮発性有機化合物)と呼ばれる室内の有機化学物質の総量を考えることが重要になります。
日本ではホルムアルデヒド放散量に関する建材の安全基準として「F★★★★(エフフォースター)」という基準があるため、これについてもあわせて確認するとよいとのことです。
近年では高気密な住宅が増えていることもあり、揮発した化学物質が室内に滞まりやすくなっているため、より注意が必要です。
木材の壁材は見た目の人気に加え、適切に使えば住む人の健康面に良い影響があります。
ただし、木の種類や乾燥方法、使用量などをよく考えて使わないと、逆に住む人にとって悪影響を及ぼす場合もあります。
何の目的で木材を使うのか、見た目なのか、効能なのか、それをよく考えて選ぶことが重要になります。
効能などの説明がなく「木材をふんだんに使っています」のような謳い文句の場合は、注意が必要とのことです。
「もみの木ハウス・かごしま」さんで使用している壁材
もみの木ハウス・かごしまさんでは、社名にもあるように「もみの木」の木材を壁材・内装材に使っています。木材はもみの木しか使わないとのことです。
自然乾燥のもみの木には、調湿効果や抗菌効果があります。もみの木にどういう成分が入っているのかというデータに基づき、床面積の200%という、程よい効能が得られる使用量を計算して使っているとのことです。
そしてもみの木を使わない部分は紙クロスの「オガファーザー」「土佐和紙」を使用されています。これらには特別な効能がないため、「もみの木の効能を邪魔しない」という特性があります。
壁材選びは、どのような目的でその壁材を選ぶのかということをしっかり持っておくことが重要になります。
見た目で選ぶのか、効能で選ぶのか、この記事を参考にしっかり考えて、壁材を選んでみてください。
参考:竹下社長の快適家づくり通信 / もみの木ハウス・かごしま 公式