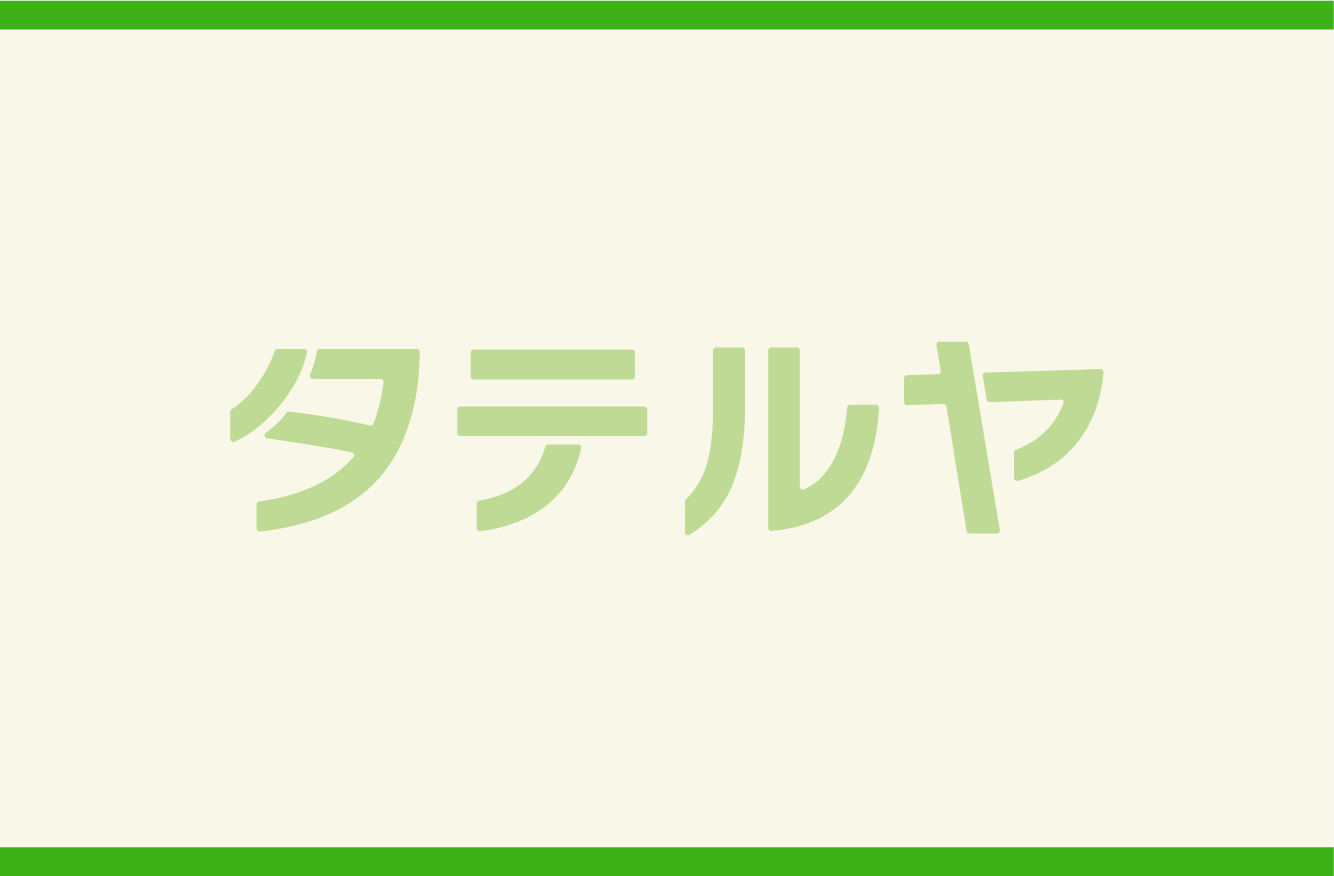宮崎で「木の家・無垢材の家」を建てられる工務店ガイド
宮崎は全国有数の杉の産地であり、中でも「飫肥杉(おびすぎ)」は樹脂分が多く、弾力性・耐湿性に優れた木材として知られています。シロアリにも強く、家づくりに適した素材です。
温暖で日照時間の長い宮崎では、こうした地元木材を活かした「木の家」づくりが盛んです。ただし、台風や梅雨といった自然条件もあるため、通気性・耐久性・防水性にも配慮した設計が求められます。こうした環境に合わせてつくられる木の家・無垢材の家は、四季を通じて快適で、家族の健康にも配慮された暮らしができる住まいとして、30〜40代のファミリー層から高い支持を得ています。
このページでは、宮崎で木の家・無垢材の家を建てるために知っておきたいポイントや坪単価の目安、地域密着型の工務店の選び方まで、わかりやすくご紹介します。
子育て世代に「木の家」が選ばれる理由とは?
家づくりを考えるとき、「安心・快適な環境で子どもを育てたい」と考えるご家庭は多いはず。そんな希望を叶えてくれるのが、「無垢材や自然素材を使った木の家」です。
木の香りややさしい肌触り、そして空気をきれいに保つ調湿効果は、小さなお子さんがいる家庭にもぴったり。自然と共に暮らす感覚を、毎日の生活の中で実感できます。
木の家・無垢材の家の魅力
木の家は、五感にやさしいだけでなく、長く快適に住み続けられる住まいでもあります。
特に、機械を使わずに風や太陽熱などの自然の力で乾燥させた天然乾燥の木材には、木が本来もっている効果が残りさまざまなメリットが得られます。
- リラックス効果:木の香りには、自律神経を整える働きがあり、住む人の心身にやさしい空間を作ります。
- 自然の調湿機能:無垢材は湿気を吸収・放出する性質を持ち、夏も冬も快適な湿度を保ってくれます。
- 省エネ性能:木材は断熱性にも優れており、冷暖房効率の向上にもつながります。
- 安心素材:ホルムアルデヒドなどの有害物質を含まない素材を使えば、シックハウス対策にも効果的。
- 経年美化:住むほどに味わいが増す木の風合いは、家族の思い出と一緒に育っていきます。
天然乾燥材のメリット・デメリット
天然乾燥材(AD材)は、伐採した木を風通しの良い場所で半年から数年かけて自然に乾燥させたものです。ゆっくり時間をかけて乾燥させるため木の細胞が壊れにくく、木材本来の風合いを保てる点が特徴です。しかし、乾燥に長期間を要することから供給量が限られ、管理コストもかかります。
天然乾燥材のメリット
調湿性が高い
木の細胞構造が保たれているため、室内の湿気を吸ったり吐いたりする調湿効果に優れます。天然乾燥材は呼吸するように湿度を調整し、室内を快適な環境に保ちます。梅雨時の湿気や冬場の乾燥を和らげる効果が期待できます。
香りや手触りが良い
高温乾燥をしていないぶん、ヒノキやスギが持つ天然の芳香成分が損なわれず残ります。木の持つ油分も流れ出にくいため表面がしっとり滑らかで、素足で歩いても心地よい質感です。経年しても色ツヤが良く、美しい木目を楽しめます。
粘り強く長持ち
ゆっくり乾燥させることで木材内部に急激な収縮が起こりにくく、木が本来もつ「しなやかな強度(粘り)」が保たれやすいとされています。多少の曲げやねじれにも追従しやすく、衝撃に対して折れにくい性質があります。また芯材に含まれる樹脂成分(油分)も保持されるため、木材自体の耐久性が増しシロアリの忌避効果も期待できます。ヒノキやヒバなど元々耐虫・耐腐食性が高い樹種では、天然乾燥材を用いることで防蟻処理剤を減らす取り組みもあります。
天然乾燥材のデメリット
乾燥後も含水率が高め
天然乾燥では木材中の水分(含水率)を人工乾燥ほど下げられないため、一般に含水率約15~20%程度が限界です。木材内部にある程度水分を含んだ状態で家に使われるので、建築後に室内環境に馴染みながら水分が抜けていきます。その過程で収縮が起こりやすく、見えない所で構造材が痩せたり縮む可能性があります。特に高気密・高断熱の住宅では木材が乾燥収縮して隙間が生じ、気密性に影響する恐れもあります。
反りや割れ(狂い)が発生しやすい
自然任せの乾燥ゆえにどうしても含水率のバラつきが生じ、使用中も周囲の湿度に応じて木材が膨張・収縮します。その結果、表面のひび割れや材の反りが起きやすくなります。これらは木が「呼吸」している証拠とも言えますが、仕上がりの精度が要求される現代の住宅ではデメリットと捉えられます。柱や梁に生じる乾燥割れ自体は強度に直ちに問題ない場合が多いものの、見た目や建具の納まりには注意が必要です。必要に応じて背割り(あらかじめ木材に割れ誘導の切れ目を入れる加工)などで割れをコントロールする対策も取られます。
乾燥に時間とコストがかかる
伐採から数年単位の乾燥期間が必要なため、生産効率が低く在庫管理の手間もかかります。乾燥中にカビや腐朽菌に侵されて材をロスするリスクもあり、歩留まりを確保するための広い保管場所も必要です。その結果、乾燥期間や保管環境に手間がかかるため、市場流通量が限られ、価格はやや高めになる傾向があります。宮崎のような湿度の高い地域では十分に乾燥させるのにより長い期間を要するため、計画段階からゆとりを持つことが求められます。
人工乾燥材のメリット・デメリット
人工乾燥材(KD材)は、木材乾燥機(キルン)に入れて高温の空気や蒸気を循環させ、短期間で木材を乾燥させたものです。一般的に数日~数週間で含水率15%前後まで乾燥させることができ、現在流通する構造用木材の大半は人工乾燥処理されています。近代的なプレカット工場で加工しやすい均一な品質に仕上がるため、多くのハウスメーカーが採用しています。
人工乾燥材のメリット
乾燥が早く安定供給できる
機械乾燥により木材を短期間で大量生産できるのが最大の利点です。製材後すぐに乾燥させて出荷できるため、建築工程を待たせずに安定した供給が可能です。材ごとに狙った含水率まで意図的に下げられるので品質のばらつきも少なく、計画通りの強度・寸法で施工できます。工期が短い現代の住宅事情に合った効率的な乾燥法と言えます。
含水率が低く構造が安定
人工乾燥材は内部までしっかり乾燥させてあるため、含水率15%以下(用途によっては10%台前半)にまで下げることもできます。その結果、施工後の収縮や狂いが起きにくく、反り・ねじれによる変形や隙間の発生を抑えられます。高気密住宅でも木材が大きく動かないため、気密性・断熱性の維持に有利です。表面割れも出にくく、仕上がりの見た目が安定しています。
カビ・虫害のリスク低減
乾燥工程で高温処理を行うことで、木材中の虫卵や木材腐朽菌の活動を抑制できます。十分に乾燥した木は腐りにくくシロアリにも狙われにくくなります(シロアリは湿った木を好むため)。そのため人工乾燥材は構造材の初期不良(カビ・虫食い)のリスクが低いです。新築時に防腐防蟻処理を併用すれば、長期間にわたり安心して構造躯体を支えてくれるでしょう。
人工乾燥材のデメリット
木の香りや風合いが損なわれる
高温で乾燥させる過程で、水分と一緒に木が持つ天然成分(油分や香り成分)が抜け落ちてしまいます。その結果、天然乾燥材に比べて木の香りが薄れ、色合いや光沢も乏しくなりがちです。極端に言えば「工業製品」のような仕上がりで、しっとりとした肌触りよりも少しカサついた感触になります。室内に木の香りを満たしたい方には物足りなく感じるかもしれません。
調湿効果が低い
木材内部の細胞構造が変化することで、天然乾燥材に比べて調湿性能はやや低下する傾向があります。専門家の間では「人工乾燥した木材は調湿性が弱くなる」と指摘されることもあります。人工乾燥材主体の住宅では、木材そのものの調湿効果が限定的になるため、快適な室内環境を保つには換気システムや調湿建材の活用がより重要となります。
内部割れ・強度低下のリスク
人工乾燥は基本的に木材の強度を高めますが、過度な高温乾燥や短い乾燥スケジュールで無理に水分を飛ばすと、かえって木材内部にひび割れが発生し強度低下を招く恐れがあります。特に厚みのある柱や梁では、表面が先に乾燥し硬化することで内部に引張応力が生まれ、内部割れ(内部裂け)が起きやすいのです。結果、乾燥条件によっては曲げ強度や圧縮強度がやや低下し、天然乾燥材に比べて長期的な耐久性に影響を及ぼす可能性もあると指摘されています。ただし現在市販されている構造用乾燥材は乾燥工程の管理がなされており、適切に使えば住宅の寿命(数十年規模)において問題ない強度は確保されています。過乾燥になりすぎないようメーカーが乾燥条件を調整しています。
樹種によっては耐虫性が低下
ヒノキやスギの芯材に含まれる殺虫・防腐効果のある成分(芳香油や樹脂分)は、高温乾燥によって揮発・減少してしまうため天然乾燥材に比べるとシロアリへの抵抗力が下がるとも言われます。人工乾燥したヒノキの土台でシロアリ被害が確認された事例もありますが、使用環境や防蟻処理の有無によって影響は異なると考えられます。
コストと環境負荷
人工乾燥は乾燥機設備の導入や化石燃料エネルギーを使った加熱が必要なため、その分コストと環境負荷が発生します。通常は流通量が多いため価格は抑えられていますが、燃料価格の高騰時には製造コストが上乗せされ、場合によっては天然乾燥材より高価になることもあります。またCO₂排出など環境面を重視する方にとっては、自然エネルギーで乾燥させた木材の方が魅力的に映るかもしれません。
【まとめ】木材選びのヒント
どちらが絶対に優れているというものではなく、重視するポイントによって最適な選択が変わります。以下に紹介する観点を踏まえて、ご自身の家づくりに合った木材を選ぶヒントにしてください。
自分たちの優先順位を考える
「木の香りや質感を存分に味わいたい」「自然素材で健康的な空間にしたい」のであれば天然乾燥材が適しています。一方、「とにかく長持ちして反りや割れの少ない家にしたい」「高気密高断熱で性能重視の家にしたい」場合は人工乾燥材が無難です。まずは家族で何を大事にしたいか(デザイン/香りか、メンテナンス性か、コストか)優先順位を話し合ってみましょう。
構造材と内装材で使い分ける
選択肢として、構造躯体は安定性の高い人工乾燥材を使い、内装の仕上げや床板には香りや肌触りを楽しめる天然乾燥材を採用する方法もあります。特に直接肌に触れるフローリングや柱の見える仕上げ部分に天然乾燥材を使うと、木の温もりを感じられる空間になります。一方、構造体は壁に隠れて見えなくなるため、品質管理された人工乾燥材を使っても見栄えの問題はありません。用途に応じて使い分けることで、コストと性能のバランスを取ることができます。
地域の気候風土に合わせる
宮崎のような高温多湿な地域では、調湿性の高い天然乾燥材は室内環境を快適にする助けになります。ただし湿度が高い分、木材自体が含む水分も高めになりやすいので、適切な換気や除湿対策が重要です。逆に冬季に乾燥しやすい地域では、天然乾燥材が水分を放出して室内を和らげてくれるメリットがあるでしょう。地元の工務店や製材所に相談して、その地域ならではの木材のベストな乾燥方法を聞いてみるのも有効です。現地の気候風土を知り尽くしたプロなら、地域材の特性も踏まえたアドバイスをしてくれるはずです。
予算との相談
木材選びは予算にも直結します。天然乾燥材は希少性ゆえに割高になりやすいですが、一部に採り入れる程度であれば大きくコストアップしないケースもあります。また最近では乾燥技術の向上や工務店独自のルートにより、天然乾燥材でも価格を抑えて提供している会社もあります。見積もりの際に「どの部位にどの乾燥方法の木材を使うか」を確認し、価格と性能のバランスが納得できるプランを選びましょう。
信頼できる業者選び
最後に大切なのは施工業者の姿勢です。天然乾燥材の良さを活かすには適材適所の設計と施工上の配慮が欠かせませんし、人工乾燥材でも過乾燥による品質低下に注意して選定する必要があります。地元で木材にこだわった家づくりをしている工務店やビルダーなら、実例を見せてもらいながら説明を受けると理解が深まります。実物の木を触って比べてみることも大事です。香りの違いや質感はカタログだけでは分かりにくいので、モデルハウスや施工現場でAD材・KD材の両方を体感してみましょう
両者の特徴を理解し、ライフスタイルや好みに合った木材を選ぶことで、家族が安心して快適に暮らせる住まいになります。天然乾燥材と人工乾燥材それぞれのメリット・デメリットを踏まえ、「自分たちの建てたい家」にふさわしい木材をぜひ検討してみてください。
木の家のメリットをわかりやすくチェック!
子どもが安心して過ごせる「空気のきれいな家」
自然素材で空気に配慮してつくられた家は、化学物質の発生が少なく、アレルギーの心配も軽減できます。
調湿効果で年中快適
無垢材が湿気を吸ったり放出したりすることで、室内環境が安定し、冷暖房に頼りすぎない暮らしが可能になります。
経年変化を楽しめる「味わいある暮らし」
年数が経つごとに木目や色味が深まり、「家と一緒に育つ」喜びが感じられます。
宮崎の「木の家・無垢材の家」建築費用相場・坪単価シミュレーション
「自然素材の家は高そう…」というイメージを持つ方も少なくありませんが、最近はコストバランスを工夫した工務店も多く、手が届く価格帯での提案も可能です。
宮崎で「木の家・無垢材の家」を建てた場合の一般的な相場
| 延床面積 | 坪数 | 総費用目安 | 坪単価目安 |
|---|---|---|---|
| 30坪 | 約99㎡ | 約2,100万〜2,300万円 | 約70〜80万円 |
| 35坪 | 約115㎡ | 約2,400万〜2,600万円 | 約70〜85万円 |
| 40坪 | 約132㎡ | 約2,700万〜3,000万円 | 約75〜90万円 |
※使用する素材や間取りの自由度、工務店ごとの仕様によって変動があります。
宮崎で「木の家・無垢材の家」を建てるなら
理想の家づくりを実現するためには、ビルダー選びがとても重要です。特に木の家を検討する際は、以下のポイントをチェックしましょう。
木の家を建てる工務店・ハウスメーカーの選び方
自然素材の標準仕様がどこまで含まれているか
無垢床や漆喰壁が標準か、オプションかでコストも変わります。
設計の自由度・提案力
自由設計にどれだけ対応できるか、自分たちのライフスタイルをどう形にしてくれるか。
価格・予算感のわかりやすさ
「坪単価だけでなく総費用ベースで説明してくれる」会社だと安心。
施工実績・地元対応力
地元の気候風土を熟知している会社なら、災害への備えやメンテナンス面でも安心です。
アフターサポート・保証制度
住んだ後の点検や相談体制なども比較材料に。
木の家で始める、家族の健やかな暮らし
毎日の暮らしにやさしい素材を取り入れた木の家は、家族が安心して暮らせる空間をつくる第一歩。自然と共にある住まいで、子どもたちの健やかな成長と、家族の豊かな時間を育んでいきましょう。
まずは気になる会社から「資料請求」してみましょう
「この会社、良さそうだけど、もっと詳しく知りたい」
そんなときは、気になる会社に3〜7社ほど資料請求してみるのがおすすめです。
各社のカタログや施工例を比べることで、プランの方向性や予算感、自分たちの価値観と合うかが見えてきます。
また、宿泊体験ができるモデルハウスや、無垢材の使い心地を体感できる見学会・体験イベントなどを開催している会社もあります。ぜひ気軽に予約・相談してみてください。